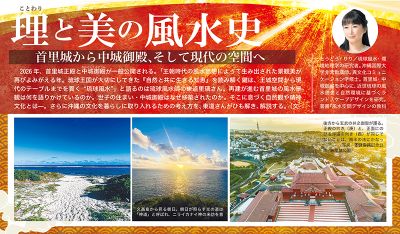地域情報(街・人・文化)
2025年11月14日更新
ちぎると白い乳液 一度はびこると除草は困難 沖縄の畑や道端で見られる帰化植物は|身近で見られる帰化植物㉜
文・写真/比嘉正一 沖縄文化スポーツイノベーション(株)顧問
海外から入ってきて、今では県内で普通に見られる帰化植物を解説。今回はトウダイグサ科のシマニシキソウとハイニシキソウを紹介します。どちらもちぎると白い乳液がでます。これはトウダイグサ科に共通する特徴です。

ちぎると白い乳液
「シマニシキソウ」「ハイニシキソウ」
シマニシキソウ/熱帯アメリカ原産

小さな花が群生する

シマニシキソウの葉。中央にうっすらと赤茶色の斑が入ることが多い
最もよく見られる
トウダイグサ科のシマニシキソウは熱帯アメリカ産の植物です。幕末に長崎県へ侵入し、その後、沖縄に入ったと思われます。
高さ10~30センチに成長します。花はとても小さく、白・赤・緑色で年中咲きます。
葉は楕円(だえん)形で、葉先がとがっています。長さは1.5~4センチ、ふちに赤茶色の斑(ふ)が入っていることが多いです。
葉や茎をちぎると白い乳液が出ます。子どものころは、この乳液が擦り傷に良いと聞いたので、足や手の傷に擦り付けていました。ただし、医学的根拠があるわけではありません。逆にかぶれることもあるようなので、マネしないでください。
シマニシキソウは畑、路傍、花壇など、ニシキソウの仲間では最も普通に見ることができます。
ハイニシキソウ/熱帯アメリカ原産

ハイニシキソウの草姿。繁殖力が旺盛で、除草は難しい

ハイニシキソウは葉も花もとても小さい
タムシに効く草
ハイニシキソウも同じく熱帯アメリカ原産です。方言名はグチャファグサといい、「タムシ(グチャファ)」に効く草という意味です。1960年代に九州に侵入し、その後沖縄に入ったと思われます。
高さ10~20センチ程になる1年生草本で、花は葉の付け根に付きます。果実は小さな三角形です。葉は長円形で長さは4~8ミリ程度と小さいです。シマニシキソウと同じように葉や茎をちぎると白い乳液が出ます。これはトウダイグサ科の仲間に共通する性質です。
畑、路傍、公園、荒れ地などに多く生育し、はびこると、除草するのはかなり難しいです。抜いても、しばらくしたらまた群生するくらい繁殖力が強いです。
**********************************
11月~12月の公園情報
※諸事情で日時が変更になる場合があります。問い合わせ先にご確認ください。
【八重島公園(沖縄市)】
◆秋のチョウ類自然観察会
・日 時/11月15日(土)午前9時30分~同11時
・料 金/1000円
・定 員/15人(小学生以上対象)
・講 師/比嘉正一氏(学芸員)
秋はチョウ類の種類・数とも1年のうちで最も多くなる時期。園内を散策しながらチョウを探して種類や数を調べる。楽しく、学びの多い観察会
・電 話=098-979-7680
【名護城公園(名護市)】
◆海を渡るチョウ・アサギマダラの話
・日 時/12月6日(土)午後1時30分~同3時
・料 金/1000円
・定 員/10人(小学生以上対象)
・講 師/比嘉正一氏(学芸員)
鳥が渡りをするように、アサギマダラも海を渡り移動することが調査から分かっている。同公園にも初夏は南西風で南から、秋には北東の風で北からやってくる。渡るきっかけや調査方法、結果などを解説する。
・電 話=0980-52-7434
【中城公園(北中城村)】
◆海を渡るチョウ・アサギマダラの話
・日 時/12月13日(土)午後1時30分~同3時
・料 金/1000円
・定 員/10人(小学生以上対象)
・講 師/比嘉正一氏(学芸員)
※同上
・電 話=098-935-2666
**********************************

執筆者
ひが・まさかず/1956年生まれ。月刊誌「緑と生活」、東南植物楽園勤務を経て沖縄文化スポーツイノベーション(株)顧問に。沖縄昆虫同好会会長、NPO法人沖縄有用植物研究会理事
毎週金曜日発行・週刊タイムス住宅新聞
第2080号・2025年11月14日紙面から掲載