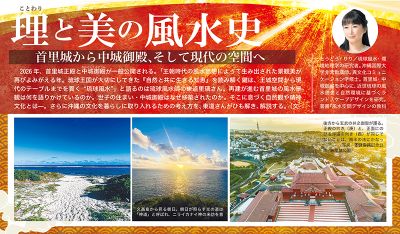地域情報(街・人・文化)
2025年9月5日更新
意外と忘れがち 携帯トイレの備え|アウトドア×減災㉙
那覇市曙にあるアウトドアショップ「燈人(ともしびと)」のスタッフ・與那嶺康貴さんが「アウトドア×減災(災害による被害を少しでも食い止めるような行動や取り組み)」をテーマに執筆。今回は備えの中でも基本的な「携帯トイレ」について。水や食料と同様に大切ですが、備蓄している人は少ないようです。

意外と忘れがち 携帯トイレの備え
さまざまなメーカーが販売「簡易トイレ」

簡易トイレは災害時だけでなくトイレがないところでも重宝する
今日まで「防災週間」
9月1日は関東大震災の発生日をきっかけとして「防災の日」に制定されており、8月30日~9月5日は「防災週間」となっています。
この機会に、お住まいの地域や職場、学校など各エリアでの防災マップの見直しや備蓄品の在庫、賞味期限などを確認してください。その際に過去の記事を参考にしてみてください。タイムス住宅新聞のウェブマガジンで、過去の当連載をすべて見ることができます=下記参照。
さて、今回は防災グッズの中に用意しておきたい「携帯トイレ」について紹介します。
日本での水洗トイレは普及率93%を超えており、レバーをひねると水が流れ、下水処理施設まで運んでくれます。毎日、当たり前のように使っていますが、こうした水洗トイレのおかげで「衛生的」「臭いを抑える」「害虫の発生や侵入を防ぐ」などの恩恵を受けています。
しかしひとたび災害が起き「停電・断水・配管破裂(上下水)」などが起こると、水洗トイレは機能しなくなります。そうなると排せつ物の処理が滞り、臭いや害虫発生など不衛生な環境となります。
過去の災害ではトイレ使用を我慢しようと「水分や食事を取らない」などの二次被害も大きな問題となりました。
備蓄している人は2割
そんなとき、「防災バッグ」や「防災ボトル」に用意しておいた携帯トイレが頼りになります。「携帯トイレ」は、便器にビニール袋を設置して使用する使い捨てトイレです。袋内に排せつし、吸水シートや凝固剤で大小便を吸収したり固めたりして廃棄しやすくしています。
一方で(一社)日本トイレ協会の報告書によると、水や食料を備蓄している人は多いのに対し、災害時用のトイレを備蓄しているのはわずか2割ほどだったそうです。同協会や国はトイレの備蓄を呼びかけています。
用意する量は「1人当たり1日5回(成人の平均排せつ回数)×7日(国が推進する日数)=35回分」が目安となります。
県内のお店を回りましたが個包装の他に10個入りや50個入りなども販売していました。いろいろなところで販売している「携帯トイレ」ですが、1度実際に使用してみるといいかもしれません。かく言う私も携帯トイレ自体は用意はしていたものの一度も使用したことがないため、この防災の日をきっかけに使い方を確認してみようと思います。
携帯トイレの他にトイレットペーパーや消毒液(ウエットティッシュ)なども一緒に用意しておくことをすすめます。今年の防災週間には是非「携帯トイレ」も追加して用意したり、使ってみたりしてみませんか?

製品によって異なるが、一般的には汚物入れ(黒い袋)、処理袋(白い袋)、凝固剤のセットになっている。

基本的な使い方は、便座に汚物入れをセットし、排せつしたあと凝固剤で固める。汚物袋を取り出して処理袋に入れて廃棄する
※当連載の過去記事をすべて見ることができます。これまでの記事はこちらから。
執筆者プロフィル

よなみね・やすたか/沖縄ヤマハ内のキャンプギアコーナー「燈人(ともしびと)」スタッフ。
那覇市曙1-8-10
電話=098・866・5365
https://sites.google.com/view/tomoshibito/
毎週金曜発行・週刊タイムス住宅新聞
第2070号・2025年9月5日紙面から掲載