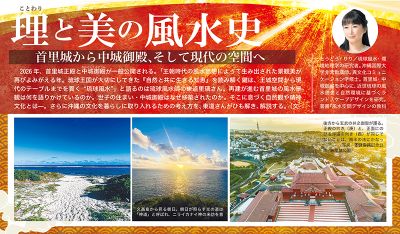地域情報(街・人・文化)
2025年10月3日更新
マイカーを災害時のプライベート空間に アウトドア店店員が「車中泊」を考えてみた|アウトドア×減災㉚
那覇市曙にあるアウトドアショップ「燈人(ともしびと)」のスタッフ・與那嶺康貴さんが「アウトドア×減災(災害による被害を少しでも食い止めるような行動や取り組み)」をテーマに執筆。今回は減災の観点から、「車中泊」の注意事項について紹介します。

減災的「車中泊」 寝場所の確保大事
自家用車で「車中泊」のレイアウトしてみた

自分の車で車中泊用のレイアウトを考えてみました。助手席を倒して、後部座席やラゲージまで使えば寝袋を広げて横になれる空間を確保できそうです
プライベート空間に
まず初めに、津波などの避難や災害時での避難所への移動などは基本的に「徒歩」が推奨されています。車での移動中に道路が渋滞してしまうと身動きが取れず逃げ遅れる恐れがあることや、道路に放置された車両が救助車両の妨げになる可能性があるため、などの理由があるようです。
災害時において、車は「移動手段」というよりも「プライベートスペース」として利用してみてはいかがでしょうか? 車内にいれば雨天時でもぬれずに過ごすことができますし、燃料があればシガーソケットからの充電やカーオーディオによるラジオ受信なども可能です。また、避難所での集団生活だと難しい「プライバシー確保」「施錠できる空間で貴重品の保管」「小さな子どもや介護が必要な家族がいる場合にも気兼ねなく過ごせる」「ペットと一緒に避難できる」などのメリットが過去の災害でも報告されているようです。
足伸ばせるよう工夫を
駐車場所によっては、トラブルになることもありますので、車中泊をする場合は周辺環境に十分に配慮してください。そして傾斜地を避け、できるだけ平らな場所に停めましょう。寝るときは車のエンジンを切るのが原則です。騒音や一酸化炭素中毒のリスクを防ぐためです。
車はキャンピングカーなどでない限り、就寝するために作られていません。水分などを取らずに狭い座席で長時間、同じ姿勢でいると血栓ができて肺に詰まってしまう「エコノミー症候群」発症のリスクがあります。時々、体を動かしたり、まめに水分を取ったり、寝るときは足を上げるなどの対策が必要です。他にも密閉された狭い空間なので「熱中症や低体温症」「一酸化炭素中毒」などにも注意が必要です。そのため、車中泊はあまり推奨されておらず「やむを得ず」の手段として考えた方がよさそうです。
もし、車で寝ることになったら「足を伸ばせる場所」の確保も大切です。座席の位置の調整や、ラゲージ(荷物を置く荷室)空間もうまく使うなどの工夫をしてみましょう。段差ができてしまう場所はクッションやタオル、衣類などを使ってフラットにするほか、足元のスペースには備蓄品を入れたボックスを置くなどしてかさ上げするのもおすすめです。
そして、プライバシー確保のために窓は目隠しすることを勧めます。マグネットやひも、フックなどを利用すると付け外しが容易です。シート以外にも銀マット(表面にアルミを加工したマット)を窓のサイズにカットして張ると、遮光や防寒にも効果的です。
いざというときのため、自家用車で「車中泊」のレイアウトを考えてみるのもいいかもしれませんよ。

なるべくフラットな状態になるよう座席を倒した=左
どうしても段差ができてしまう場所はかさ上げし、上にクッションやタオルを敷くなどの工夫を=右
どうしても段差ができてしまう場所はかさ上げし、上にクッションやタオルを敷くなどの工夫を=右
※当連載の過去記事をすべて見ることができます。これまでの記事はこちらから。
執筆者プロフィル

よなみね・やすたか/沖縄ヤマハ内のキャンプギアコーナー「燈人(ともしびと)」スタッフ。
那覇市曙1-8-10
電話=098・866・5365
https://sites.google.com/view/tomoshibito/
毎週金曜発行・週刊タイムス住宅新聞
第2074号・2025年10月3日紙面から掲載