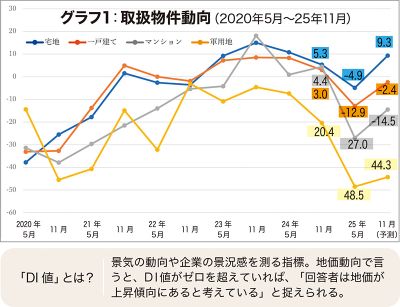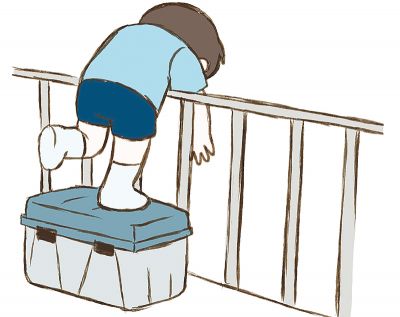地域情報(街・人・文化)
2025年4月25日更新
[セグロウリミバエ]ウリ科植物の栽培自粛呼び掛け|生果実 本島外への移動規制
沖縄本島中北部で、海外から侵入した農作物の害虫「セグロウリミバエ」が確認されている。ウリ科の植物などに寄生し、定着してしまうとゴーヤーやナーべーラーなど、沖縄を代表する農作物に大きな被害を及ぼす恐れがある。県は早期の根絶に向けて家庭菜園でのウリ科植物の栽培自粛を呼び掛けているほか、国は4月14日から対象植物の生果実を本島外へ持ち出すことを規制している。
セグロウリミバエ
ウリ科植物の栽培自粛呼び掛け
ウリ科植物の栽培自粛呼び掛け
生果実 本島外への移動規制
沖縄本島中北部で、海外から侵入した農作物の害虫「セグロウリミバエ」が確認されている。ウリ科の植物などに寄生し、定着してしまうとゴーヤーやナーべーラーなど、沖縄を代表する農作物に大きな被害を及ぼす恐れがある。県は早期の根絶に向けて家庭菜園でのウリ科植物の栽培自粛を呼び掛けているほか、国は4月14日から対象植物の生果実を本島外へ持ち出すことを規制している。多くが家庭菜園から
セグロウリミバエは、ゴーヤーやヘチマ、キュウリ、スイカやメロンなどのウリ科植物などに寄生する害虫だ。沖縄本島で2024年3月に確認されて以降、中北部で少しずつ生息地を広げている。「そのほとんどが家庭菜園から見つかっている。家庭菜園は農薬散布や防虫ネットなどの防除対策が手薄なことから、寄生されやすい」と県農林水産部・営農支援課の担当者は指摘する。
セグロウリミバエの成虫。体長は8〜9ミリ(沖縄県農林水産部資料)
県内では過去にウリミバエがまん延し、根絶までに長い年月が掛かった。それを繰り返さないため、県は昨年12月から家庭菜園でのウリ科植物栽培の自粛を呼び掛けている。「庭や畑に自然に生えているもの(ナンクルミー)も除去してほしい。また、ウリ科果実の中にウジ(幼虫)を見つけたら、すぐ県の関係機関=下囲み=に連絡してほしい」と話す。

◆今年は、家庭菜園や緑のカーテンなどでウリ科植物を栽培するのは控えよう

◆一般家庭からウリ科植物や左記の植物を本島外へ送ったり、持ち出したりすることは原則、できない。12月31日まで。延長する恐れもある
◆ウリ科果実の中にウジ(幼虫)を見つけたら、すぐに下記へ連絡を
| ◆セグロウリミバエについての問い合わせ先 沖縄県農林水産部 営農支援課 電話=098・866・2280 沖縄県病害虫防除技術センター https://www.pref.okinawa.lg.jp/shigoto/nogyo/1010700/index.html 電話=098・886・3880 |
本島外へ持ち出し禁止
4月14日からは「ウリ科植物など=下記=の沖縄本島外への移動規制」も始まった。対象の農作物は、行政の検査に合格しなければ本島外へ移動(出荷)できない。違反すれば3年以下の懲役か、100万円以下の罰金を科せられる恐れがある。
ゴーヤー、カボチャ、ズッキーニ、ヘチマ、スイカ、トウガン、キュウリ、メロン、モーウイなど
◆上記作物以外で、沖縄本島外への持ち出しができない植物
サヤインゲン、トマト、ピーマン、トウガラシ、パパイヤ、パッションフルーツ、ドラゴンフルーツ、グァバなど
「基本的に、一般家庭からゴーヤーやスイカなどの対象植物を県外や離島へ送ったり、持ち出したりすることはできないと考えていただきたい」と県の担当者は説明する。対象作物を入れた段ボール箱などの梱包に検査合格証明ラベルが貼り付けされたものであれば持ち出し可能だが、この梱包から果実を出してしまうと持ち出しできなくなる。
移動規制は今年12月31日までの予定だが、根絶できなければ延長の恐れもある。「現在は発見地周辺で殺虫剤を散布したり、誘殺板の設置などを進めているほか、6月からはウリミバエ根絶に大きな役割を果たした不妊虫放飼法も実施する」と説明。
「いつまでに根絶させる、という明確なスケジュールを提示できないのは申し訳ないが、生息域が限定的な今のうちに抑え込みたい。県民の皆さまにおいては、まず今夏は家庭菜園でのウリ科植物の栽培自粛や、移動規制などにご協力いただきたい」と力を込めた。
毎週金曜発行・週刊タイムス住宅新聞
第2051号・2025年04月25日紙面から掲載