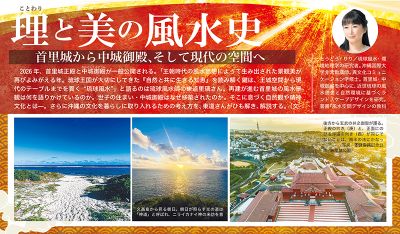建築
2025年2月14日更新
[2025年の変]家造りに新たな基準|沖縄の気候に合った省エネ住宅 独自基準の策定へ議論|内外を緩くつなぎ 住環境を整え
4月から新築住宅にも省エネ基準適合が義務化される。「高断熱・高気密」が推進され、沖縄独自の家づくりの技術・知恵の継承が困難になると危惧される。これを受け、(公社)沖縄県建築士会は昨年12月、那覇市で公開研究会を開き、建築実務者らと意見交換。独自の省エネ住宅「気候風土適応住宅」基準を策定し、来年度からの運用を目指す。

気候風土適応住宅や省エネ基準などについて説明を行った、(左から)琉球大学の清水肇教授、北海道立総合研究機構の鈴木大隆理事、NPO法人蒸暑地域住まいの研究会の金城優理事長

68人の建築事業者らが公開研究会に参加し、「沖縄の気候風土適応住宅」の基準について意見を交わした
熱・光を和らげる緩衝空間
気候風土適応住宅とは省エネ基準適合が難しい伝統木造住宅に重点を置き、設けられた制度。
一方で、沖縄ではコンクリート造の建物が普及しており、その技術が蓄積されている。さらに日射熱が建物に伝わる前に遮へい、通風により内部の熱や湿気を逃がすなど住環境を整えてきた。
こうしたことを背景に、琉球大学の清水肇教授は「全国一律の基準に則るのではなく、沖縄独自の基準を策定・普及させることで、環境負荷も抑えた省エネ住宅につながる」と述べた。国が提示しているのは「高断熱・高気密型」の省エネ住宅だが、「蒸暑地域の沖縄では『緩衝領域型住宅』が気候風土に適している」とモデルを示した=下図。

「緩衝領域型」は断熱化により外皮(外気に接する屋根や外壁、窓など)性能を強化するのではなく、「深い軒によるアマハジ空間や花ブロックで囲んだ外部空間などで外皮自体に熱を伝えない『緩衝空間』を設ける。内外の境界を曖昧にし、太陽熱・光の浸入を和らげる」と清水教授は説明した。
条件異なるがゆえ 建築力を
国の省エネ基準策定などに関わっている北海道立総合研究機構の鈴木大隆理事は基調講演で、気候風土適応住宅の認定基準を満たす手法などを解説。
評価されている建築要素は現在、「アマハジ」だけだが、検討段階のものに、伝わる太陽熱・光を抑えつつ通風を確保する「花ブロック」、「屋根通気ブロック」など地域生産の建材がある。鈴木さんは「全国で唯一、沖縄は地域から省エネ住宅・気候風土適応住宅のあり方を問える。本土と大きく異なる気候・建築条件下で、培われてきた『建築力』を存分に発揮してほしい」と語った。
建材運搬からCO2減らす
NPO法人・蒸暑地域住まいの研究会の金城優理事長は、気候風土適応住宅のスムーズな運用のためのチェックシートの案を提示。建築士らが必要な項目を満たしているか確認することができ、建築確認申請を受け付ける行政庁もその適応の度合を把握することにつながる。
続けて、「省エネ住宅は生産過程で発生するCO2の量も考慮するべき」とも。地震や大型台風など災害に襲われ、「建て直す際、国が提示する省エネ住宅の仕様だと建材の運搬などが必要となり、排出されるCO2の量は増加。建物のライフサイクル全体で環境負荷が増えるだけではなく、施主の経済的負担も増す。耐久性を高め、建物を長寿命化することも大切」と指摘した。
県は本研究会の内容や設計実務者らの意見をまとめ、「気候風土適応住宅」基準を策定し、来年度からの運用を目指す。
毎週金曜日発行・週刊タイムス住宅新聞
第2041号・2025年02月14日紙面から掲載