家づくり
2025年10月3日更新
新築工事も折り返し コンクリートの型枠が外された後、お楽しみが|Aさんの家づくり 完成までの道のり⑦
マイホームの建築は人生の一大事業。住まいづくりについて皆さんのヒントになるように、建築士の具志好規さんがAさん宅完成までの流れを紹介します。(文・写真/具志好規)
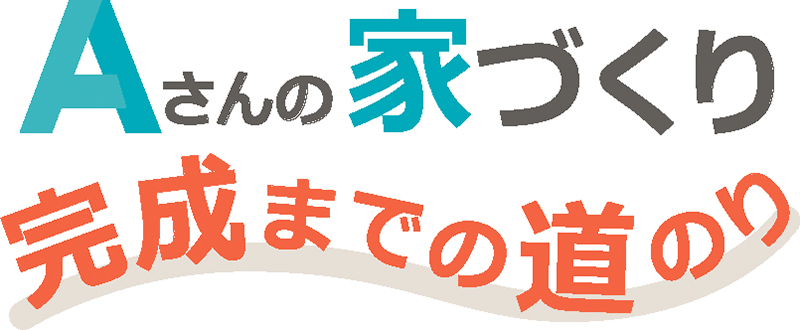
雨仕舞いを終えて工程の折り返し
型枠外し迫力の空間を体感
棟上げ後、壁などの側面は打設から3日、梁(はり)下やスラブ底は3~4週間ほど養生期間を置く。その後、圧縮試験でコンクリートの強度を確認し型枠の解体がスタートする。壁は枠を締め付けている鋼管、スラブ底は支えているサポートパイプを取り外して、型枠をコンクリートから剥がす。解体された型枠の木材は、分別され再利用される。

スラブ下の型枠の解体作業。落ちてくる型枠に注意しながら慎重に作業をしていた
全ての型枠が外れると、私たちはコンクリートがきれいに入っているか出来型の確認を行う。建物の全貌が現れ、イメージしていた空間を実際に体感できる楽しみな瞬間でもある。Aさん家族も現場を訪れ、建物全体を覆う大きな屋根と、広く迫力ある空間を見てとても感動していた。

型枠解体後、パティオから建物内部を見る。外部と内部に連続した屋根が空間を一体にしている

型枠解体後の建物内部の様子。実際の現場はイメージしていた空間より広く、開放的に感じた
次に、内部足場を組んでアルサッシを取り付け、ガラスを入れて雨仕舞い(内部に雨水が浸入しないように防水処理をする)の工事が進む。サッシなどの開口部は単に明かり取りや、通風のためだけではなく、建物の外観や内部からの見え方、部屋の広さや天井の高さも踏まえて大きさや位置、形状を決めている。

アルミサッシの取り付けの様子。レーザーで傾きや位置を確認し、溶接して固定する
外の景色を見せたいパティオとダイニングは、天井までの大開口の窓を採用し、内外の天井とトップライトを連続して見せることで空間が一体となり、より広く見せることができる。逆に和室やリビングは外部からの視線を遮り、座った目線で坪庭の植栽がきれいに見えるよう低めの窓にしている。トップライトは壁面の窓と比べて多くの光を取り入れる事ができる。さらに室内部分は光を拡散させるため、乳白色のフィルムも貼った。日中は照明が必要ないほど明るい空間になった。

トップライトに取り付けられたガラス。飛散防止のため外部には透明、内部には乳白色のフィルムを貼った
大開口は注意も必要
Aさんの家は大開口の窓を使うことで明るく開放的な建物だが、大開口の採用は通常の窓より安全性に配慮するため、サッシやガラスの強度に注意する必要がある。沖縄では風速46メートルの風に耐えることが一般的な強度基準だが、私たちは過去に宮古島の台風で観測された最大風速85メートルを基準とし、サッシには補強材を入れ、厚いガラスを使用することで強度を高める対策をしている。今回の現場で一番大きなガラスは大きさが約3平方メートル、厚みは15ミリ、重量は120キロ弱である。サッシとガラスを入れたおさまる総合建材の奥平誠代表は「この建物がどう仕上がるのか完成が楽しみで」と取り付けた後も頻繁に現場を見に来ていた。
これで工事は約半分まで進み、Aさんの家づくりは中間地点を折り返した。

アルミサッシとガラスを取り付けて雨仕舞いが完成。工事の前半が終わり、後半の仕上げ工事に入る
執筆者プロフィル

ぐし・よしのり
1981年、那覇市生まれ。沖縄職業能力大学校住居環境科卒、(有)チーム・ドリーム勤務。住宅・商業施設・教会や公共施設など幅広く設計に関わっている。
https://www.dream-archi.com
今回のサッシやガラスの強度のように、建物は間取りや環境条件などに応じて仕様を考えることが大切だ。耐久性に関わることは、特に注意している。
毎週金曜発行・週刊タイムス住宅新聞
第2074号・2025年10月3日紙面から掲載












